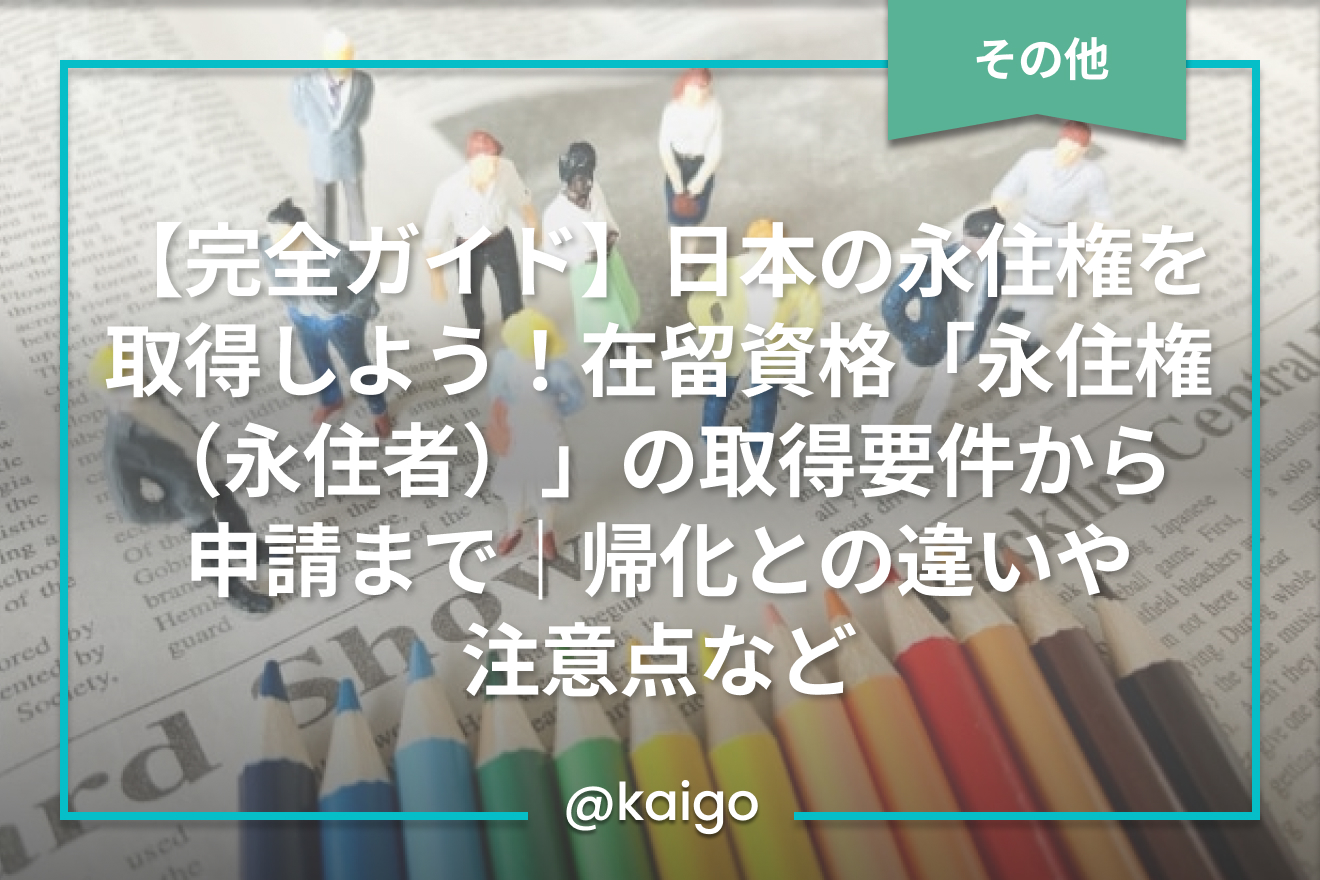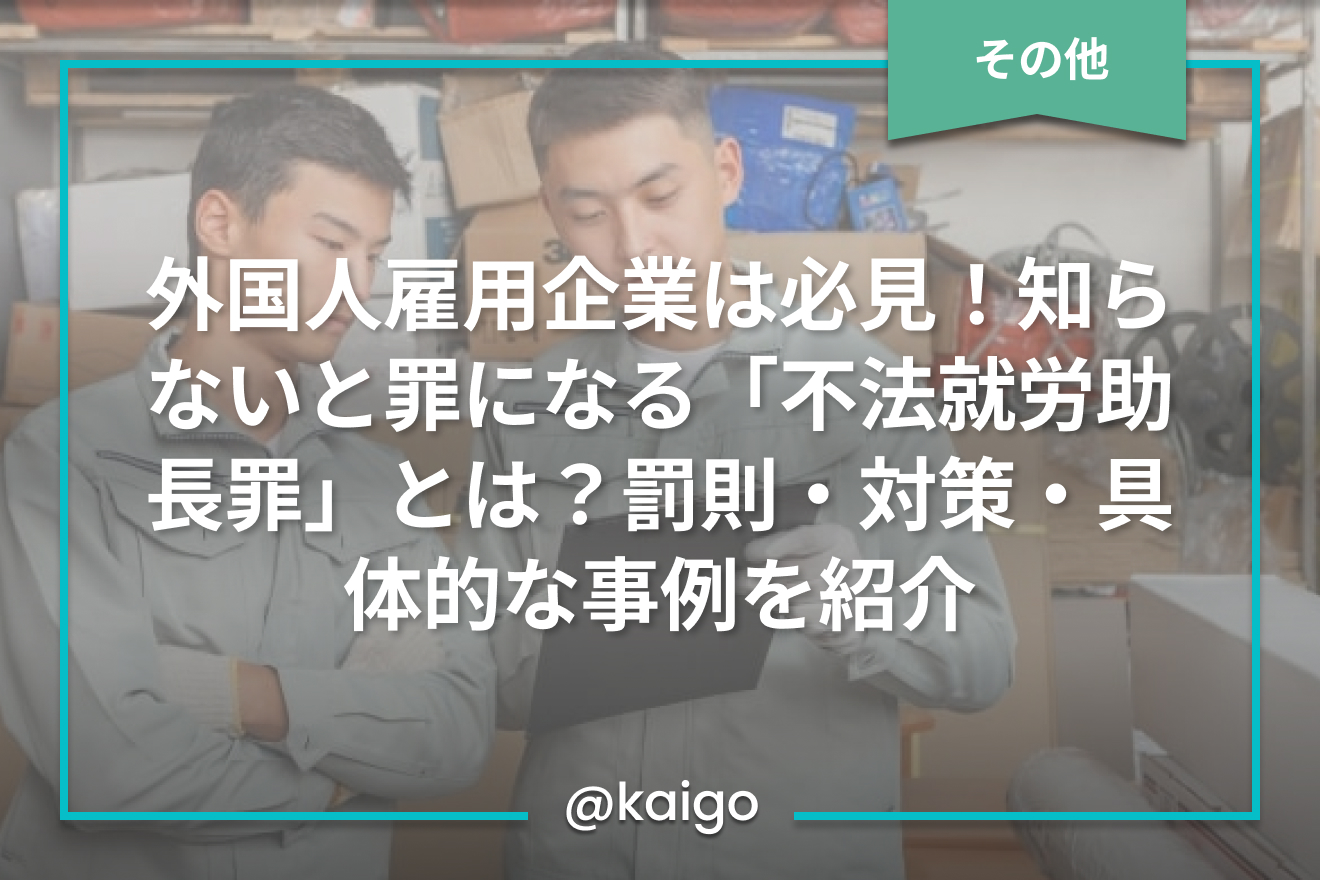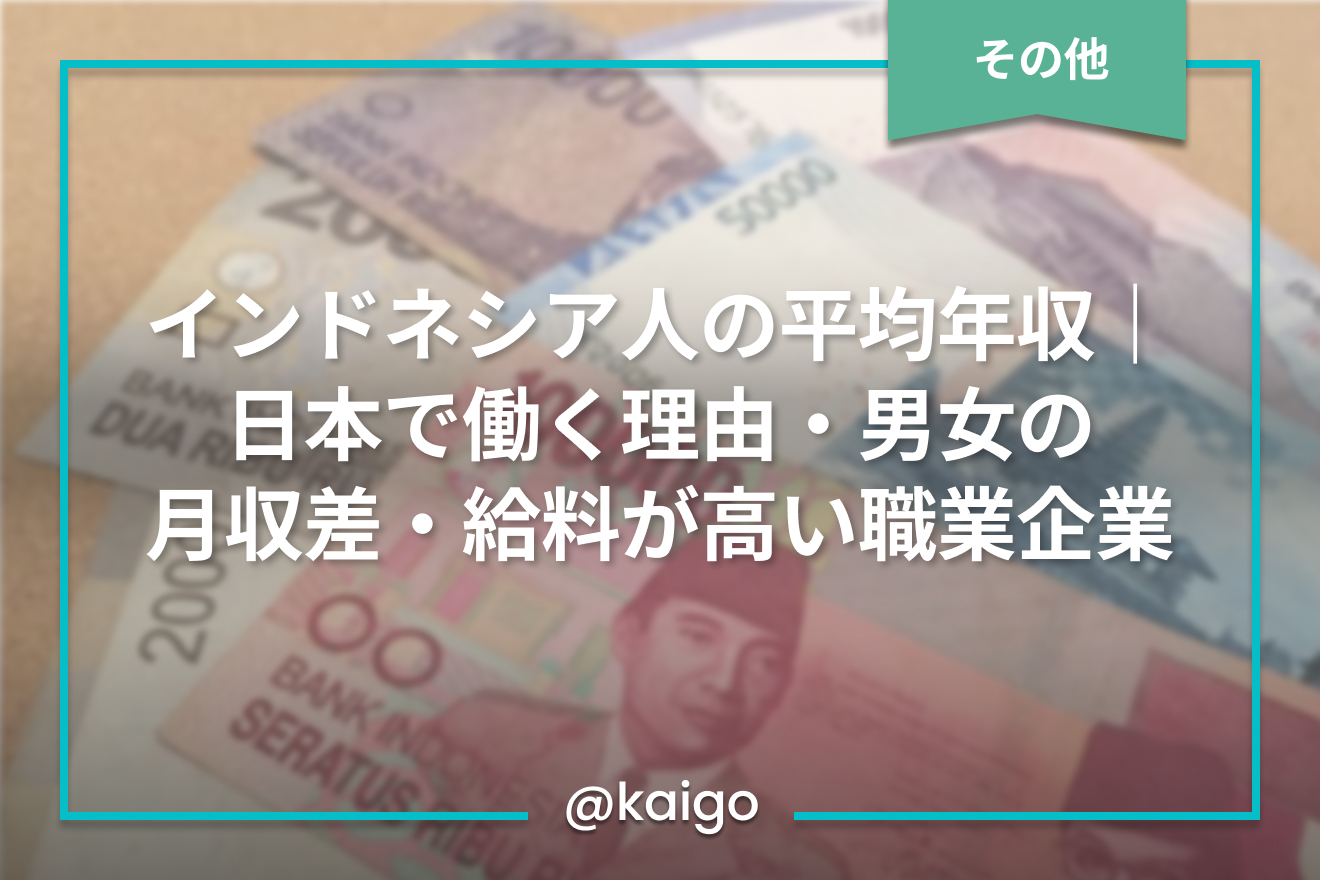コラム
外国人就労ビザを更新するには?申請の流れから必要書類、条件までを詳しく解説
その他
 2024/11/30
2024/11/30 2025/4/15
2025/4/15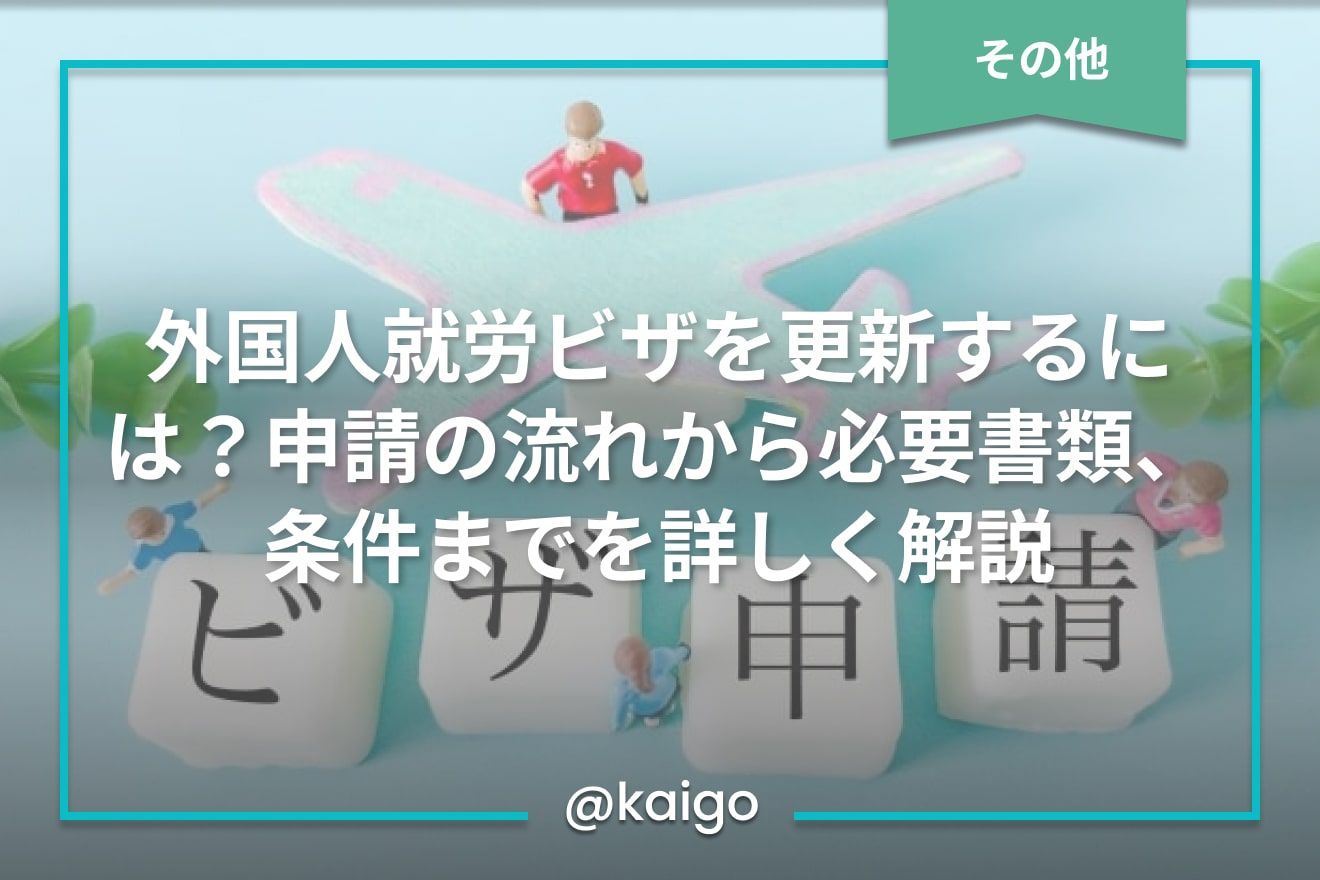
就労している外国人のビザの更新期限が近づいているとき、「何をいつまでにすべきなのか」「手続きにはどのくらい時間がかかるのか」と不安を抱えるかもしれません。
就労ビザの更新は、外国人の状況により必要な書類が異なります。必要な書類が多く、更新の許可も時間がかかるものです。
本記事では、ビザ更新に必要な書類や更新の流れなどをまとめました。参考にしてください。
目次
日本で外国人のビザ更新問題と長期雇用について

外国人の就労ビザには、在留期間が設けられています。長期間就労する場合は、定期的にビザの更新が必要です。職種、企業、年収によって在留期間が異なるため、自社で働く外国人の更新時期の把握が求められます。一般的に在留期限の3か月前から更新手続きが可能です。
更新手続きを忘れ、在留期間を過ぎると、不法滞在の扱いになります。強制退去や刑事罰を命じられるため注意しなくてはなりません。
ビザの更新に必要な申請は、次の4パターンに分かれます。書類の不備を防ぐため、就労する外国人がどのパターンであるかを把握してください。
| ①ビザ取得時と同じ職場・業務にて更新するケース | ②転職したがあらかじめ「就労資格証明書」を取得しているケース | ③同じ職種に転職して「就労資格証明書」を取得していないケース | ④以前とは異なる職種に転職しているケース | |
| 必要な手続き | ・在留期間更新許可申請 | ・在留期間更新許可申請
・「就労資格証明書」を添付する |
・在留期間更新許可申請書
・前職と現職の企業が発行する書類の添付 |
・在留資格変更許可申請
・前職と現職の企業が発行する書類の添付 |
| 詳細 | ・転職や業務内容に変更がなく、ビザ取得時と同じ職場、業務内容で働くケース
・現在と同じ在留期間で更新する場合が多い(1年・3年・5年のいずれか) ・現在よりも長期の在留期間も申請できる |
・同じ職種で転職したケースで、すでに「就労資格証明書」の手続き済み
・あらかじめ取得した「就労資格証明書」を添付すれば「在留期間更新許可申請」と同じ手続きで済む ・更新不許可となるケースが少ない |
・同じ職種だが、異なる職場に転職しているケース
・「就労資格証明書」を取得できてない場合、ビザ更新時に必要な書類が増える ・「業務内容」と「給与」が審査されて更新不許可となるケースもある |
・ビザ取得時と職場・業務内容に変更がある場合
・「業務内容」と「給与」が審査され更新不許可となるケースもある |
とくに、③④のケースは、要注意です。外国人が所有する在留資格に対し、「勤務先の職種や従事する業務が適正か」を審査されます。「適正ではない」とされると、更新不許可となり、帰国しなくてはなりません。
以降の章では、それぞれのケースにおける、申請方法や必要な書類を解説します。
① 職場・職種に変更がなく就労ビザの在留期間のみ更新
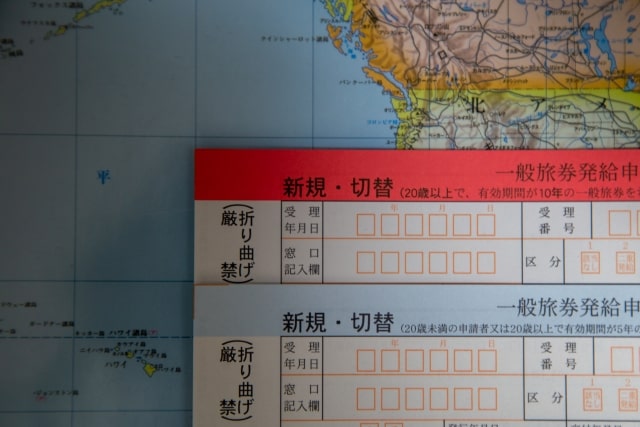
職場や職種に変更がなく、在留期間のみ更新するケースです。
「出入国在留管理局(旧:入国管理局)」に必要書類を提出し、更新手続きをします。
日本で犯罪を犯したり、納税漏れがない限り、2週間〜1ヶ月にて更新を許可する旨のハガキが届きます。
用意する書類は、次のとおりです。
| 書類名 | 詳細 |
| 在留期間更新許可申請書 | ・「申請人用」シートは外国人が記載し署名する ・「所属機関作成用」は会社が記載し社印を捺す ・3ヶ月以内に撮影した外国人の顔写真を添付 |
| パスポートと在留カード(原本・コピー) | ・原本は当日提示 ・コピーを提出 |
| 外国人本人の証明写真 | 4センチ×3センチ |
| 在職証明書 | ・就労先が発行 |
| 住民税の課税・納税証明書 | ・1月1日時点で居住している役所にて取得可能 ・納税証明書に課税額の記載がある場合は、課税証明書は不要 ・非課税対象者の場合は非課税証明書を添付 |
| 税務署の捺印がある就労先の法定調書合計表 | ・企業が社員などの源泉徴収をとおし納税した合計金額が記載された書類(個人の源泉徴収票ではない) ・年に一度企業が税務署へ提出している ・税務署の捺印があること ・電子提出で捺印がない場合は「受付した旨のメール」を印刷して添付 |
②転職したが「就労資格証明書」を取得している場合の就労ビザ更新

外国人は転職時に、「就労資格証明書」を取得しているケースがあります。その場合、ビザ更新時の必要書類は次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートと在留カード(原本・コピー)
- 外国人本人の証明写真
- 在職証明書
- 住民税の課税・納税証明書
- 税務署の捺印がある就労先の法定調書合計表
- 就労資格証明書
職場・職種に変更がないケースと同等の手続きで済むため、非常にスムーズです。
転職時、在留期間に余裕がある際は、「就労資格証明書」の取得を推奨します。
就労資格証明書とは
「就労資格証明書」は、転職した際に就労資格証明書交付申請をすることで取得できます。
この申請は、「新たに勤務する会社の業務が、現在の在留資格に該当するか」を確認するための手続きです。
事前に「就労資格証明書」の手続きをしていない場合、在留期間の更新時に突然不許可となる場合があります。その際、帰国や早急な転職活動が求められます。
手続きの際、用意する書類は次のとおりです。
| 書類名 | 備考 |
| 就労資格証明書交付の申請書 | ・会社に記載してもらう箇所はなく本人のサインのみ |
| 前職の退職証明書 | – |
| 前職の源泉徴収票 | – |
| 転職先の雇用契約書 | ・従事する業務、雇用期間、役職と報酬の記載が必須 |
| 転職先の会社概要がわかる資料 | ・3ヶ月以内に発行された法人登記簿謄本 ・決算書の写し(会社設立1年以内の場合は事業計画書) ・事業内容がわかるパンフレット |
| 理由書 | ・転職した理由を記載 ・転職先で従事する業務内容を記載 |
| パスポート | – |
| 在留カード | – |
申請後の審査期間は、1ヶ月程度です。無事に許可されると「交付許可」のハガキが届きます。その後、「交付されたハガキ」と「1200円分の収入印紙」を出入国管理庁へ提出すると、「就労資格証明書」をもらえます。
一般的に、ビザの更新期限まで1〜2年ある場合には、就労資格証明書交付申請をするケースが多いです。更新期限まで4ヶ月以上余裕がある場合は、突然の不許可を避けるためにも、申請を推奨します。
③同じ職種に転職して「就労資格証明書」を取得していない場合の就労ビザ更新

在留期限が3ヶ月を切ったときの転職は、就労資格証明書交付申請に充てる時間がありません。その際、ビザ更新時に転職先の業務内容が、現在の在留資格に該当しているかどうかを確認します。
ビザ更新時の提出書類は、次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書
- パスポートと在留カード(原本・コピー)
- 外国人本人の証明写真
- 在職証明書
- 住民税の課税・納税証明書
- 税務署の捺印がある就労先の法定調書合計表
- 就労資格証明書
- 前職の退職証明書
- 前職の源泉徴収票
- 転職先の雇用契約書(業務、雇用期間、役職と報酬の記載)
- 転職先の法人登記簿謄本
- 転職先の決算書の写し(会社設立1年以内の場合は事業計画書)
- 転職先の業務内容がわかるパンフレット
- 理由書
注意点は、在留資格と業務内容の合致だけでなく、外国人の学歴・職歴との合致も確認されることです。
具体例をあげると、日本の専門学校でプログラミングを学び、「技人国ビザ」でシステムエンジニアとして就労していた外国人の場合、転職先で商品開発の業務に従事するとき、更新不許可となるケースがあります。
技人国ビザは、次の業務に従事できるビザです。
| 技術 | 人文知識 | 国際業務 |
| ・システムエンジニア ・機械工学の技術者 ・プログラマー ・セキュリティーの技術者 |
・企画 ・営業 ・経理 ・人事 ・法務 ・総務 ・コンサルティング ・広報 ・マーケティング ・商品開発 |
・通訳 ・翻訳 ・デザイナー ・貿易 ・語学学校などの語学講師 ・ホテルでの通訳業務 |
このとおり「商品開発」も技人国ビザの業務に当てはまります。ただ、外国人の学歴、職歴とは異なる分野のため、更新が許可されません。
ビザ取得時に満たした条件(※)は、転職先でも満たし続けることが求められます。
※
技人国ビザ取得時の場合、日本の専門学校・短大・大学大学院の卒業と、学歴に関連した専門的な業務に就くことが求められます。
④異なる職種に転職して「就労資格証明書」を取得していない場合の就労ビザ更新
就労先だけでなく、職種も大きく変更する場合は、「在留資格変更許可申請」を用意します。つまり、異なるビザへ変更しなくてはなりません。この手続きは、「留学ビザ」でアルバイトとして就労していた留学生を、ビザ更新のタイミングで社員として雇う場合も当てはまります。
この時に必要な書類は、次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 変更予定の在留資格に応じた申請書・資料を提出(※)
- パスポートと在留カード(原本・コピー)
- 外国人本人の証明写真
- 在職証明書
- 住民税の課税・納税証明書
- 税務署の捺印がある就労先の法定調書合計表
- 就労資格証明書
- 前職の退職証明書
- 前職の源泉徴収票
- 転職先の雇用契約書(業務、雇用期間、役職と報酬の記載)
- 転職先の法人登記簿謄本
- 転職先の決算書の写し(会社設立1年以内の場合は事業計画書)
- 転職先の業務内容がわかるパンフレット
- 理由書
在留資格の変更が認められると、新たな在留資格の規則のもと在留期間を更新できます。
※
在留資格に応じた申請書や資料は、在留資格によって異なります。
出入国管理庁「在留資格変更許可申請」のページを合わせてご確認ください。
在留資格変更許可について
在留資格変更許可は、申請さえすれば、ビザを変更できるわけではありません。
ビザの取得に必要な条件を、外国人が満たしていることが求められます。
特に、介護事業とWEB開発事業といった、複数事業を展開する企業の場合、注意が必要です。
例えば、在留資格「介護」で介護福祉士として働く外国人に、WEB開発事業に取り組む関連会社へ移籍してもらう場合です。プログラミングが得意で、問題なくWEB開発の仕事に従事できたとしても、それだけでは「技人国ビザ」へ変更できません。
「技人国ビザ」の取得条件となる、プログラミングの学校卒業、またはプログラミングの実務経験が10年以上を満たす必要があります。
業務に従事できる能力があったとしても、条件を満たしていないと不許可となる点にご注意ください。
ビザ更新のスケジュール

本章では、ビザ更新のスケジュールを解説します。大枠の流れと申請当日の流れ、おおよその時期がわかるため参考にしてください。
ビザ更新の流れ
ビザ更新の大枠の流れは、次のとおりです。
| 手順 | 詳細 |
| ①出入国在留管理局にて相談 | ・転職した場合、事前に相談しておくことを推奨 ・事業内容や従事する業務内容がビザと合致しているかを相談 |
| ②書類を作成 | ・外国人が申請書や理由書などを用意する ・更新するケースに伴い会社で必要な書類を発行 ・前職の会社に発行してもらう書類があるときは、協力依頼する |
| ③申請書へ署名と捺印 | ・必要な書類を用意したら外国人と会社それぞれが記名捺印 |
| ④出入国管理庁にて申請 | ・作成した書類とパスポート、在留カードを持参して出入国管理庁へ提出する |
| ⑤新しい在留カードの発行 | ・許可された場合約1ヶ月後にハガキが届く ・ハガキとパスポート、在留カードを持参して出入国管理庁へ再度出向く ・出入国管理庁にて新しい在留カードを受け取る |
ビザ更新における当日の手続きの流れ
出入国管理庁にて書類を提出する手続きは、長時間に及びます。具体的な当日の流れは、次のとおりです。
- 整理券配布の列に1時間程度並ぶ
- 申請書類をチェックされ揃っていれば整理券をもらえる
- 数時間待機する
- 順番が来たら再度申請書類のチェックがあり、揃っていれば受理
基本的には半日がかりになると把握しておきましょう。書類に不備がある場合には、一度持ち帰らなくてはなりません。
その場合、後日同じ手順を踏んで、申請します。
ビザ更新の時期とかかる期間
ビザを更新できる時期と、ビザ更新までにかかる期間は次のとおりです。
| ビザ更新時期 | ビザ更新までにかかる期間 |
| 在留期限の3ヶ月前から期限が切れる前日 | 3週間~2か月程度 |
ビザを更新できる時期は、在留期限の3ヶ月前から前日までです。期限が切れる数日前に申請した場合、更新許可を待つ間に期限が切れてしまうことになります。
その際、最大2ヶ月間の「特例期間」があります。在留カードの裏に「在留期間更新申請中」と捺印されていれば、2ヶ月間は猶予される仕組みです。
新しい在留カードの受け取り期限は、許可が降りてから2ヶ月以内となります。
また、ビザの更新を行政書士などへ依頼するケースもあります。その場合、申請と受け取り時に、外国人本人が出入国管理庁に出向く必要がありません。
ただし、申請と受け取りのタイミングで、日本国内にいることが求められます。
就労先によっては、海外出張などで出国しなくてはならないケースがあります。その場合、更新申請後、特例期間であれば出張も可能です。
ただ、出入国管理庁から、本人の住所当てに「追加書類の提出依頼」が届く場合もあります。ハガキが郵送される住所は、申請時に指定できるため、会社宛にするなどの配慮が必要です。
ビザ更新にかかる費用
ビザの更新にかかる費用は、4,000円で、収入印紙にて用意します。
申請が許可され、新しい在留カードを受け取る際、収入印紙4,000分を出入国管理庁へ提出します。
就労ビザの更新を企業が代理する方法/h2>
外国人の日本語力によっては、更新を1人でおこなうのは難しいかもしれません。その際、ビザの更新を企業が代理することもできます。
ここでは、代理申請のポイントをまとめました。
申請取次の許可を受ける
ビザの更新を代理申請するときは、「申請取次の許可」を受ける必要があります。
そのためには、「申請等取次研修会」に参加しなくてはなりません。
研修会に参加することで、修了証書が交付され、ビザ更新の代理申請が可能となります。
研修会の参加にかかる費用は、17,600円です。公益財団法人入管協会の公式ホームページから申し込みできます。
就労ビザを代理申請するとき費用は企業が負担する?
ビザ更新にかかる費用を、本人と会社どちらが負担すべきか迷うかもしれません。
法的な決まりはなく、どちらが費用を負担しても良いとされています。そのため、代理申請後、外国人へ更新費用4,000円を請求することも可能です。
ただ、企業側が外国人との長期的な雇用契約を希望する場合は、企業側が負担することが多いです。
状況に合わせて検討しましょう。
就労ビザの更新が難しくなるケース【要注意】

必要な書類を漏れなく用意しても、ビザの更新が不許可となる場合があります。事前にケースを知っておくことで、出入国管理庁へ相談できます。
不許可となるケースを把握し、就労する外国人が該当していないか確かめてください。
刑事罰に課された
就労する外国人が、罪を犯して刑事罰に課されたとき、ビザを更新できないことがあります。
更新のガイドラインには「素行については、善良であることが前提となる」と記載されています。
何か犯罪を犯してしまった場合、更新が難しいと判断しましょう。
不法就労している
不法就労している場合も、更新を認めてもらえません。不当就労には、次の3パターンがあります。
| 不法就労となるケース | 詳細 |
| 不法滞在の外国人が就労している | ・密入国した外国人が働いている ・ビザが切れているのに滞在して働いている |
| 認められていない業務に従事している | ・在留資格に当てはまらない業務に従事している ・在留資格で認められる時間を超えて働いている |
| 就労不可の外国人が就労している | ・本来であれば就労が許可されていない在留資格なのに働いている ・観光目的の短期滞在ビザ滞在なのに働いている |
企業側も故意ではなく、認められていない業務に従事させてしまうケースがよくあります。
介護分野の特定技能を例に挙げると、「夜勤」や「訪問介護」は認められていないのに、知らずに夜勤に従事させてしまうケースです。
不法就労は、更新の不許可以外に、罰則が課されます。外国人と企業に課される罰則は、次のとおりです。
| 外国人 | 企業 | |
| 不法滞在の場合 | 3年以下の懲役、もしくは禁錮、もしくは300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、場合によっては両方 |
| 資格外の業務に従事した場合 | 1年以下の懲役、もしくは禁錮、または200万円以下の罰金 | |
この場合、会社の経営が困難になります。外国人を受け入れる時は、不法就労に注意しましょう。
在留カードを紛失してから再発行していない
在留カードを紛失したのに、再発行していないとき、ビザの更新ができない場合があります。
在留カードを紛失したら、14日以内に再交付手続きをおこなわなくてはなりません。
忘れているだけでも、手続きを怠ったとみなされます。紛失した際は、気づいた時点で速やかに再発行しましょう。
ちなみに再発行の手続きは、次の手順を踏みます。
| 手順 | 詳細 |
| ①最寄の交番へ届出 | ・警察署や交番へ紛失届を出す ・遺失届出証明書をもらう |
| ②出入国在留管理庁へ再交付の申請 | 次を持参して手続きする ・在留カード再交付申請書 ・遺失届出証明書 ・顔写真 ・パスポート |
再交付の手続きも、申請取次の許可を受けていれば企業が代理でおこなえます。
また、在留カードは常に携帯しておかなくてはなりません。警察官に提示を求められて不携帯のとき、20万円以下の罰金となるケースもあります。
ビザの更新に影響するため、注意が必要です。
税金の滞納
税金を滞納している(していた)場合、ビザを更新できないことがあります。
特に税金は、1年前の収入をもとに納税額が決まります。留学生のアルバイトでは、収入が安定せず、納税が難しい時期があるかもしれません。
ビザ更新時に提出する課税証明書に「納期到来未納額」があるとき、不許可となる可能性があるため注意が必要です。
納税できない特別な事情がある場合は、その時点で役所に相談してください。その際、「◯◯市延滞確認」と捺印された納付書を発行してもらえます。ビザ更新時は、この納付書を持参し、事情を説明しましょう。
まとめ

就労ビザは、在留期間が切れる3ヶ月前から更新できます。申請してから結果が出るまで3週間〜1ヶ月程度の日数がかかるため、早めの更新が求められます。
「転職あり」「転職なし」や、「留学生が社員になる場合」など、それぞれの外国人によって用意する書類が大きく異なります。
日本語が不慣れな場合、外国人がすべて把握するのは困難です。会社でも更新に関する知識を身につけ、外国人をサポートしてあげましょう。サポートが難しい場合、料金はかかりますが、行政書士や登録支援機関へ依頼する方法もあります。
@ケアでは、人手不足に悩む介護福祉の企業に向けて、外国人の受け入れやその後の管理までサポートしています。
現在受け入れている外国人のビザ更新に不安がある場合も、お気軽にお問い合わせください。貴社の悩みに合わせた適切なサポートを提供します。